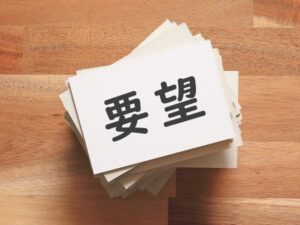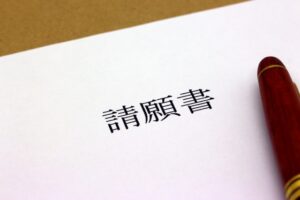化学物質過敏症の苦しみを、メーカーに届けた日
2025年5月、私の自宅前にある老人ホームの浴室から排出される強い香料臭により、
私は深刻な体調不良に陥りました。
呼吸が苦しくなり、自宅にとどまることもできず、避難先も見つからないという、
極めて追い詰められた状況でした。このような現実を、少しでも企業の皆様にご理解いただきたい。そして、互いに配慮し合える社会をともに築いていけたら──そんな願いを込めて、本メッセージをお送りいたしました。
〇〇株式会社
法務部門 コンプライアンス推進部 御中
お世話になっております。〇〇と申します。
私は化学物質過敏症(MCS:Multiple Chemical Sensitivity)を抱えて生活している者です。
合成香料や一部の化学物質に曝露すると、
呼吸困難や頭痛、倦怠感などの症状が出てしまい、
日常生活に著しい制限を受けております。近年、柔軟剤や洗剤などの香りが集合住宅や公共空間に拡散し、
私を含む過敏症患者にとって深刻な健康被害となるケースが後を絶ちません。
こうした声は私一人のものではなく、
実際にSNS上でも非常に多くの方が日々の苦しみを訴えています。総務省の調査報告書にも、
地方自治体における化学物質過敏症への対応事例が複数取り上げられており、
これは既に社会的な課題として認識されつつあることの証左です。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000142629.pdf
115ページ:事例No.18(洗剤による健康影響と自治体の対応)その他、最近ではスーパーで有機野菜の取り扱いが増えたり、
無添加・低刺激製品が選ばれるなど、
消費者の価値観も「健康」や「環境」への配慮へと着実にシフトしてきています。こうした時代の流れの中で、例えば香料に関しても、
廃棄予定の果物の皮や果肉など未利用資源を活用することで、
環境への配慮と体へのやさしさを両立できるのではないでしょうか。
これは「人」「社会」「企業」の三方にとって望ましい取り組みになると確信しております。つきましては、以下のような取り組みをご検討いただけましたら幸いです。
- 無香料・低刺激製品のさらなる展開と周知
- 香料・成分の詳細な開示(由来や使用目的の明示)
- 香りに関する啓発活動(においマナーや配慮の呼びかけ)
- 未利用資源の活用など、持続可能で人と環境にやさしい製品開発
御社のような影響力の大きい企業が先頭に立って取り組んでくださることで、
より多くの人々が安心して暮らせる社会が築かれていくと確信しております。
ご多忙の中、大変恐縮ではございますが、本件についてご検討いただけましたら幸いです。今後とも御社の社会的な取り組みとご発展を心より応援申し上げます。
何卒よろしくお願い申し上げます。〇〇〇〇
メーカーから届いた、機械的な回答
香料による体調悪化の実体験をもとに、私はメーカーに対して要望のメールを送りました。
その結果、企業のご担当者様からご返信をいただきました。
〇〇様
弊社への貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。
弊社と致しましては商品表記の一部に香りの強さ・目安などを表示するなど、
お客様に適切に商品をお使いいただけるように引き続き取り組むとともに、
業界団体である、日本石鹸洗剤工業会を通じてより多くの方々に
適切な情報がお伝えできるように活動を今後も継続して参りたいと思います。
この度はご連絡、ありがとうございました。〇〇担当
花王からの回答を受けて思うこと
正直、ある程度は予想していたとはいえ、
届いた返答には、何の中身もなく、落胆しました。
──でも、ここで少し視点を変えてみたいと思います。
企業側の立場に立って、なぜこうした対応になるのかを考察してみます。
株主への責任
大企業である以上、株主からの信頼を得ることは絶対条件。
四半期ごとの業績、株価の動き、利益率……それらはすべて、株主の評価につながります。
つまり企業にとって最大のミッションは、「利益を出し、株主に報いること」。
社員への責任
利益を出すためには、優秀な人材の力が必要です。
そのためには、給与や福利厚生といった待遇面の整備も欠かせません。
社員の満足度を高め、競争力を維持することが求められます。
消費者へのアプローチ
企業が利益を出すには、やはり「売れる商品」をつくることが不可欠です。
そこでは、「多くの消費者にウケるか」「コストを抑えて、いかに大量に売れるか」といった視点が重視され、
一部の人にとってのリスクや体への影響といった問題は、後回しにされがちです。
経営トップの視点
経営陣は、株主・社員・消費者、それぞれのバランスを考えながら、
企業全体の方向性を決めていく立場にあります。
個別の「声」が、経営判断に影響することは、実際にはほとんどないのかもしれません。
社内の構造的な壁
たとえ現場の社員が「これは問題だ」と感じたとしても、
その声が上層部に届くとは限りません。
一つの部署に要望を送ったところで、会社全体の意思決定にまでつながることは稀であり、まして経営方針が変わることなど、ほとんど期待できないのが現実です。
企業の“構造”として、声が届かないのかもしれない──
そんな疑問が浮かびました。
企業とは、いったい何のために存在しているのか。
この構造を見ていくと、どうしてもその根本的な問いにたどり着きます。
経済至上主義のなかでは、
人間の生命さえも、取るに足らない事柄として扱われてしまう。
少数の声や健康被害の訴えは、
「ビジネス上のリスク」として静かに処理され、
表に出ることなく片付けられていく。
そう考えると、いくら真摯に声を届けたとしても、
企業の構造そのものが、こうした声を受け止める土台を持っていないのかもしれません。
もちろん、これは一つの視点にすぎません。
しかし、もしそうだとすれば──
私たちは、「どこに、どう声を届けるべきか」を、
もう一度根本から問い直していく必要があると感じています。